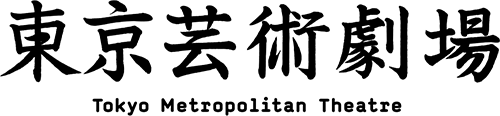- オンラインインタビュー
-
いいへんじ 俳優:松浦みるさん
今回は、「いいへんじ」より、俳優の松浦みるさんにオンラインでインタビューさせていただきました!俳優の目線から見た作・演出の中島梓織さんとはどのような方なのか、お二人の出会いと「いいへんじ」への想いも伺いました。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
松浦さん、本日はお忙しい中お時間いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします!
松浦さん(以下、松浦):よろしくお願いします!
今日(取材日:7月5日(月))は稽古はお休みとのことでしたが、進捗はいかがでしょうか?
松浦:昨日、初めてちゃんと全員揃って通しをしました。最後まで通りましたね、無事に。進捗はとても良いと思います。
順調ですね!
松浦:はい、順調です!「いいへんじ」は割といつも順調なんですよね。おぺ(中島さん)がちゃんと計画を立てて、その通りに進めてくれるので。台本もいつも本当に早いので、間に合わないと焦ったことはないです。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
中島さんのことは「おぺ」と呼んでいらっしゃるんですね。
松浦:はい(笑)。たぶんそのあだ名の由来は本人が一番喋れると思うんですけど…。「梓織(しおり)」が「しおりっぺ」から「しおっぺ」になって、だんだん縮まって「おぺ」になったらしくて。大学一年生で初めて会ったときにはもう「おぺって呼んでください」って本人が言っていたので、ずっとそう呼んでいます。
松浦さんと中島さんの出会いについてお聞かせください。
松浦:早稲田大学の同じ演劇サークル(演劇倶楽部)に同期として入りました。演劇倶楽部では、夏の新人公演に向けて稽古をして、新人公演に出たらやっと本格的に加入できるという仕組みでした。新人公演に向けた稽古をしているときは、特に仲が良かったというわけではなかったです。ただ、無印良品が好き、とか、おぺもインタビューで言っていたんですけど、「贅沢貧乏」さんの公演をお互い観に行って「良かったね」と共通の感想を持ったり、サークルの稽古以外のところで盛り上がれたのが、仲良くなる大きなきっかけだったと思います。
ずっと一緒に活動するには、好みが合うか、ウマが合うか、といったところは大事ですよね。第一印象はどのような感じでしたか?
松浦:第一印象はあんまり覚えてないです(笑)。ただ、出会って数カ月くらいの印象は、「うらやましいな」でした。サークルの同期みんなが「中島と同じシーンがやりたい」と言っていたんです。当時、エチュード(即興)というか、自分たちでシーンを作ることをたくさんやっていて、それをおぺとやるとすごく面白くなるんですよね。私も「一緒にやりたい」と思っていましたし、俳優としてのおぺのことも「うらやましいな」と思っていました。
当時からみんなに一目置かれていたんですね。そんな中島さんから一緒に「いいへんじ」をやろうと声をかけられたときは、どうでしたか?
松浦:もう、超うれしかったですね(笑)。劇団に入れたらいいなとか、誰かと一緒にやっていこうというのは思っていなかったので、自分が「やった!うれしい!一緒にやる!」と返事をしたことにも結構驚きました。予想していなかったけど、そのまま乗っかっちゃえるくらいにはうれしかったです。
二つ返事でOKだったんですね。
松浦:即答でしたね。
いいへんじのこれまでの活動について、印象的なエピソードはありますか?
松浦:私とおぺは、割と喧嘩をするんです。お互い、雰囲気よく演劇を作ろうと努めているんですけど、自分自身のことになると、色々なものを投げ捨てて演劇をやってしまうんです。お互い苦しいところに自分を追い込んで演劇をやってしまうという面があるので、「良くない雰囲気」になることもあります。だから「いいへんじ」は楽しいというだけではなく、すごく切実で一生懸命というか…。私にとってそうなれるのが今のところ「いいへんじ」しかないんです。健康に良いかと言われると、良くも悪くもだと思うんですけど、私はそういったことをすごく必要としているので、続けてしまっています。
お互い本音でぶつかりあえるというのは、すごく素敵なことだと思います。
松浦:全然今も、なんでも言い合えるような気持ちのいい関係性ではないと思うんですけどね…(笑)。2017年に「いいへんじ」の旗揚げ公演『ハイ』を上演したときに、「うお、ちゃんと苦しい!」と思って。そこから、波はあるんですけど、ずっと苦しい感じがしています。
苦しさを共に味わえる関係性、でしょうか。
松浦:そうですね。すごく貴重な存在だなと思います。……こんなこと思ってるの私だけだったらすごく恥ずかしいですね…!
こういったことは普段、カンパニーの皆さんで話されたりしますか?
松浦:たまに、要所要所で話します(笑)。最近は定期的にミーティングだったり、公演が終わったあとの反省会をするようにしているので。公演中に思っていたことは話せる場をつくるようにしています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
作品についてお伺いします。これまでの「いいへんじ」の作品は松浦さんの目にどう映っているのでしょうか?
松浦:おぺの書く戯曲で一番良いのは「言葉」で、ほぼ「しゃべり言葉」で作られているんです。それを読むだけで、もう「いいへんじ」だとわかります。そういう作品をずっと作り続けていて、かつ、おぺは「言葉」というものをいつもブラッシュアップしようとしています。だから、とにかく戯曲の「言葉」が好きだなと思うし、それはずっと変わらないです。今回も、「言葉」がいとおしいです。全部。話す単語、喋り方、順序とか、選ぶ言葉がすべていとおしいなと思います。
おぺは「俳優本人の魅力を引き出して、いとおしい人間を描きたい」と言っていて、私は出ている人間として、「かわいい」とか「いとおしい」と言われることに違和感や疑問があって。それはたぶん、私自身が「人間ってそんなにいとおしいものではなくない?」と思ってしまっている部分があるからなのかもしれません(笑)。あと、「かわいいって簡単だよな」とか。だから、このままだと私自身がちょっとまずいんじゃないかと思っていたんですね。いとおしさみたいなものが「いいへんじ」の良い部分だということもわかってはいたんですけど。
でも今回の『薬をもらいにいく薬(序章)』は、通しを見て、そういった今までとは少し違う、嫌じゃない「いとおしさ」があったんです。なんでなのかは、まだわからないんですけど…。もしかしたら、俳優がみんな誰も自分を「いとおしくみせよう」と意図していないからかもしれないですね。「これをやろう!」ということ、目の前のやるべきことに集中しているから、そういった切実さがちゃんと「いとおしく」見えるということが起こったのかもしれないです。自分のことを「いとおしい」、「かわいい」と思っている人が登場するわけではないので、当たり前なのかもしれないんですけど…。見ていて、心がぎゅーっとなりました。現実を生きる人のひたむきさ、みたいなものが感じられる作品に仕上がってきているんですね。拝見するのが本当に楽しみです。では、普段松浦さんが俳優として、作品に向き合う際に意識されていることや目標を教えてください。
松浦:「いいへんじ」の現場だと、「誰よりもおぺの書く言葉をすばらしく魅力的に扱える人になる」といつも思っています。そういう人になりたいなと。今までの作品を全部合わせて、おぺの書く台詞を1番多く喋っているのは私になると思うんですが、「おぺの言葉をすばらしく扱う」ことでは、誰にも負けたくないです。
他の現場だと、多分意識していることは毎回違うんですけど…。「おばあちゃんになるまで俳優をやろう」とは思っています。あと、今年、私は青年団という劇団にも新しく所属しまして、個人的に今すごく地方公演に興味があります。東京以外の土地で、泊まり込みで、演劇をたくさんやりたいです。良いですね、前回の「コトリ会議」さんのインタビューでも、山本正典さんが旅公演の魅力を語ってくれました。
松浦:はい、すごく良いなぁと思って読みました(笑)。「いいへんじ」としては「将来こうしていこう」というしっかりとした目標を作ることはあまりないです。私たち自身、この先どういう風に演劇をやるかわからないし、他に素敵なやりたいことができるかもしれないと思っているので。でも、どんなときでも、「いいへんじ」に戻ってきたら息ができるように、というか、何かを持ち帰れる場所にしたいなと思っています。
松浦さんご自身が演劇をやっているのは、そういった「息ができる場所」という思いがあるからなのでしょうか。
松浦:演劇が他の表現と比べて特別だということはないと思っています。たまたま私にとっては、演劇が「息ができる場所」だったというだけなんです。演劇をずっと続けているのはきっと得意だからです。大きな声を出したり、台詞を覚えたりすることが得意。得意なことや、普段生きていてつい気になってしまうことを、演劇をつくる場では無視したり隠したりしなくていい。私にとってはたまたまそれが演劇だったというだけなんです。
最後に、芸劇eyesの上演に向けた作品づくりへの意気込みをお聞かせください。
松浦:うーん意気込み…。芸劇は憧れの場所です。「弱いい派」って言われているけど、きっと弱いだけだったら芸劇ではやれていないだろうと思います。強い気持ちを持って挑戦したいです。今回、私は声の出演というかたちにはなりますが、すごくワクワクしています。
松浦さんの声が芸劇にどのように響くのか、とても楽しみです。ありがとうございました!
松浦:ありがとうございました!
「いいへんじ」の松浦さんにお話を伺いました。5歳のころに地元・福岡の市民劇団に入り、演劇を始めたという松浦さん。「ずっと続けてるといいことありますね」と話してくださいました。
次回は、「ウンゲツィーファ」さんの稽古場に潜入します。
作品タイトルが『Uber Boyz』に決まった「ウンゲツィーファ」さんが、どのように稽古をされているのか、謎に迫ります。
お楽しみに!
- 稽古場インタビュー
-
いいへんじ 作・演出:中島梓織さん

トップバッターは、「いいへんじ」作・演出の中島梓織さんです。
『薬をもらいにいく薬(序章)』の稽古場にお邪魔し、フレッシュな素顔に迫りました。中島さん、本日はよろしくお願いいたします。つたない進行で恐縮ですが、色々とお話お聞かせください…!
中島梓織さん(以下、中島):よろしくお願いします!今回はじめて私たちを知ってくださる方もいると思うので、良いきっかけになればと思っています。
ありがとうございます!まず、お伺いしたいのが、「いいへんじ」という団体名についてなのですが…由来があったりするのでしょうか?
中島:由来というものは実は特に無くて(笑)大学1年生のときに、私と松浦みる(俳優、「いいへんじ」所属)が早稲田大学演劇倶楽部というサークルで知り合ったんですけど、新人公演が終わって、自由に活動できるようになったときに、私はもともと劇作と演出がやりたいと思っていたので、「ユニットを作ろう」と。松浦に私から「一緒にやろう」と声をかけました。一緒にやっていくには名前が必要だよね、となったとき「ひらがなで、略せずに読める名前」にしようということで、候補を出し合って決めました。特にこだわりがあったわけではないんですが、「ちゃんとフルネームで呼んでほしい」という気持ちはあったかもしれないです(笑)お互い50個ずつ、思いつく単語を出し合いました。
50個も!
中島:はい(笑)そこから候補を絞って、最終的にお互いが「良いね」となったのが「いいへんじ」でした。だから意味とかは、あまり考えてなかったです。ただ、後付けですけど、「演劇をやる上で互いに応答しあうことが大事」ということはもともと考えていて、そこにたまたまはまったので「答えを出すことよりも、わたしとあなたの間にある応えを大切に」というのをキャッチコピーみたいに使うようになりました。
中島さんのこれまでの活動についてお伺いします。演劇は大学から始められたのでしょうか?
中島:本格的にはそうですね。大学1年生のときに「いいへんじ」を結成して、大学2年生のときに旗揚げ公演を早稲田大学の学生会館で打ちました。基本的には学生会館にある公演ができるスペースと早稲田小劇場どらま館を拠点に公演を行いつつ、外部の演劇祭やショーケースにも参加していました。特に大学2~3年生のときはハイペースに公演を行っていました。
大学以前は演劇と関わりはありましたか?
中島:高校生の時に演劇部に所属していました。そのときの顧問の先生から「演劇やるなら早稲田だよ」と勧められて、早稲田大学を受けて…という感じです。早稲田大学を志願しようと決めてからは、一直線でしたね。
もし演劇をしていなかったらこんなことをしていたかも、という職業はありますか?
中島:なにしてただろう(笑)難しいんですけど、学校の先生になっていたかもしれないです。中学生頃までは、周りの期待に応えようとしていたというか、典型的な「優等生」を演じていたので。中学校では生徒会長もやっていましたね(笑)
すごい!
中島:そういうイメージが外側からも出来上がっていたし、自分の中でも作っていた、というのが小学校・中学校のときはあったんですけど、そこから外れさせてくれたのが演劇でした。小・中とバスケをやっていて、体育会系のノリも自分には合っていなかったはずなのに無理をしてやっていて、もっと自分を自由に表現したいと思っていたところで演劇部に出会いました。「私のやりたいことはこれかもしれない!」と思って。そこから、約15年積み重なっていたものから徐々に解き放たれて…という。まだ完全に解き放たれきってはいないですが(笑)なので、演劇をしていなかったら学校の先生になっていたと思います。両親が教員ということもありますし、人に話したり、教えたりすることは好きなので。
作品についてお聞かせください。稽古進捗はいかがでしょうか?
中島:脚本の第1稿は上がっていて、俳優と話をしながら手直ししつつじっくり進めて行っている状況です。今日(取材日の6月20日(日))からバンバン立ち稽古を始めていこうかなと。
自分では脚本執筆は遅い方だと感じていて。なので今回は早めに、年明けくらいから手を付け始めていました。最初の構想から半年くらいかけていますね。プロットに時間をかけて、台詞を書き始めたのが4月中旬くらいからです。年を追うごとにいろいろと悩むようになってしまって、書くのが遅くなっている気がします…(笑)なので、自分で締切を決めて、周りに「この日までに上げます!」と宣言して自分を追い込みました。めちゃめちゃストイックですね…!今回の作品の内容について、お話しいただける範囲でお聞かせください。
中島:5人の登場人物がいて、その中の2人の男女を中心に進んでいきます。2人の会話の中から、社会的にいわゆる“弱者”として括られてしまうような人たちを描こうと思っています。具体的には、精神疾患を持っている方々や、セクシュアルマイノリティの方々のような社会的に“弱者”と“されてしまっている”人たちです。彼ら彼女らにも生活や望みはあって、それを「どうにかしたい」と思っているのに「どうにかできない」ままに“させられてしまっている”という現状について、凄く時間はかかるけれど、対話の中で考えていければと思っています。なので、40分の短編の中では収まりきらず、今回は長編の冒頭を上演するという形になりました。時間をかけて、おしゃべりしながら、わたしたちなりの社会に対する応答を見つけていくことができればと思っています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場にて撮影
とはいえシリアスにはなりすぎず、俳優の力も借りて、コミカルさだったり、ポップさみたいなのも出せればと思っています。ずーんと重くなりすぎないのだけれど、劇場を出るときにちょっと考えてもらえるきっかけになればいいなと。
「いいへんじ」さんは、作品の内容とそれに対する向き合い方のバランスが絶妙だなと感じるのですが、そのあたりはどう意識されていますか?
中島:最近気付いたんですけど、劇作より演出の方が好きだなというのがあって。劇作が年々キライになっているというか……。
えー!
中島:キライというか、辛くなってきている、というか……(笑)やっぱり劇作は1人の孤独な作業というか、自分の中で考えを巡らせていかなければならない、自分が普段見ないようにしているところも見るようにしなければならないので、すごく辛くなりながら書いているんです。けど、演出はすごく楽しくて。いつも稽古前に皆でおしゃべりをする時間をつくるようにしているんですね。作品に関係するようなことを稽古前に話してから、作品の稽古に入るんです。自分が書くものは、ひとりで必死になって、何かを吐き出すように書いているものなんですけど、他の人にとってはぜんぜん違う見え方になるんだなって。稽古はその発見ができる場所だと思っています。そういういくつもの発見を1つの演劇に立ち上げていくという作業がめちゃくちゃ楽しいなと、最近どんどん自覚しています。なので、演出したいから書いている、みたいなところがあるかもしれません。これをきっかけにみんなとおしゃべりをするための準備だから頑張ろう、みたいな感じで書いていて。演出をするときは、俳優のみんなを魅力的にみせたいなという気持ちがあって、何かキャラクターを演じてほしいというよりは、その人自身の魅力を引き出せたらいいなということに注力しています。テーマ自体も、「重いな、暗いな」とかではなく「興味深いな」と思ってもらえることが一番大事だと思っていますね。重そうで暗そうなものでも、演劇の形にしてみると意外とおもしろく思えてきませんか?という提示をするための演出を考えています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場にて撮影
『つまり』という作品があって、自分の実体験をそのまま赤裸々に、日記を書くみたいに書いたものなんですけど、それが出来たときは本当に恥ずかしくて。これは人様に見せられるようなものではない、という気持ちがありました。でも、逆にこれを人様に見せられる形、面白いと思ってもらえる形にするにはどうすればいいんだろう、という風に考えるようになりました。劇作家の自分に対して「なんてものを書いてくれたんだ!」という距離感で演出家の自分が演出する、みたいなことをまずは意識的にやるようにしていますね。
ご自身の生み出したものへのこだわりに対する冷静さがありますよね。影響を受けた作品などはありますか?
中島:上京してきて初めて観た演劇が、「贅沢貧乏」さんの『ハワイユ―』という作品でした。松浦も観ていましたね。山田さん(「贅沢貧乏」主宰:山田由梨)の軽やかさというか、お洒落さ、ポップさがすごく好きだなと思って。演劇や自分の書いたもの、俳優さんの魅力を「面白がる」のが上手な方なので、尊敬しています。
最初は書いている自分と演出をしている自分がごっちゃになっていたんですけど、最近は分けなきゃなと思っていて。劇作家が稽古場にいると答えがそこにあるような気がしてしまうので、「劇作家の中島梓織さんはここにはいません」みたいなことを俳優に言っていたりします。私はこの作品をみんなと一緒に読む側の人です、というスタンスでいるようにしています。俳優のみなさんがどう思っているかはわからないですけど…。自分のこだわりを皆にやってもらうというよりは、「こだわりもって書いたらしいよ!」とケラケラ笑いながら渡すような感じですね。クリエーションの中でも「応答」を意識されているんですね。最後になりますが、芸劇eyesへの意気込みを教えてください。
中島:めっちゃ緊張してます。いつもの3~4倍くらい(笑)
それはショーケース形式という部分でですか…?
中島:いや、どちらかというと我々ショーケース芸人のようなところがあるので(笑)ありがたいことに演劇祭やフェスに呼んでもらうことが多くて…。なので、そこに対してというよりは、大きい劇場でやることに緊張しています。普段は小さい劇場で、お客さんが近いところでやっているので、結構個人的なことだったり、話題として小さいことを扱っていてもあまり違和感がないというか。それをどうやって芸劇の広さで成立させるか、効果的に魅せるにはどうすればいいか、試行錯誤中です。
なるほど、芸劇という空間へどう「応答」されるのか、楽しみです。中島さん、本日はありがとうございました!
中島:ありがとうございました!
「いいへんじ」の中島さんにお話を伺いました。
稽古場ではコミュニケーションゲームや話し合いの時間がしっかりと取られているのが印象的で、「コミュニケーションの中で見つかるもの」を大事にされていることを実感しました。
等身大の口語や、言語化しづらい感覚を丁寧に台詞に起こした会話は必見です。次回ご紹介するのは、ウンゲツィーファの本橋龍さんです。
6月17日(木)~20日(日)に行われていたUL公演『トルアキ』を観劇し、終演後、お話を伺いました。
お楽しみに!
インフォメーション
-
芸劇eyes番外編 vol.3
『もしもし、こちら弱いい派 かそけき声を聴くために』日程:7月22日 (木・祝) ~7月25日 (日)
会場:シアターイースト
オンラインインタビュー
いいへんじ 俳優:松浦みるさん
今回は、「いいへんじ」より、俳優の松浦みるさんにオンラインでインタビューさせていただきました!俳優の目線から見た作・演出の中島梓織さんとはどのような方なのか、お二人の出会いと「いいへんじ」への想いも伺いました。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
松浦さん、本日はお忙しい中お時間いただきありがとうございます。よろしくお願いいたします!
松浦さん(以下、松浦):よろしくお願いします!
今日(取材日:7月5日(月))は稽古はお休みとのことでしたが、進捗はいかがでしょうか?
松浦:昨日、初めてちゃんと全員揃って通しをしました。最後まで通りましたね、無事に。進捗はとても良いと思います。
順調ですね!
松浦:はい、順調です!「いいへんじ」は割といつも順調なんですよね。おぺ(中島さん)がちゃんと計画を立てて、その通りに進めてくれるので。台本もいつも本当に早いので、間に合わないと焦ったことはないです。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
中島さんのことは「おぺ」と呼んでいらっしゃるんですね。
松浦:はい(笑)。たぶんそのあだ名の由来は本人が一番喋れると思うんですけど…。「梓織(しおり)」が「しおりっぺ」から「しおっぺ」になって、だんだん縮まって「おぺ」になったらしくて。大学一年生で初めて会ったときにはもう「おぺって呼んでください」って本人が言っていたので、ずっとそう呼んでいます。
松浦さんと中島さんの出会いについてお聞かせください。
松浦:早稲田大学の同じ演劇サークル(演劇倶楽部)に同期として入りました。演劇倶楽部では、夏の新人公演に向けて稽古をして、新人公演に出たらやっと本格的に加入できるという仕組みでした。新人公演に向けた稽古をしているときは、特に仲が良かったというわけではなかったです。ただ、無印良品が好き、とか、おぺもインタビューで言っていたんですけど、「贅沢貧乏」さんの公演をお互い観に行って「良かったね」と共通の感想を持ったり、サークルの稽古以外のところで盛り上がれたのが、仲良くなる大きなきっかけだったと思います。
ずっと一緒に活動するには、好みが合うか、ウマが合うか、といったところは大事ですよね。第一印象はどのような感じでしたか?
松浦:第一印象はあんまり覚えてないです(笑)。ただ、出会って数カ月くらいの印象は、「うらやましいな」でした。サークルの同期みんなが「中島と同じシーンがやりたい」と言っていたんです。当時、エチュード(即興)というか、自分たちでシーンを作ることをたくさんやっていて、それをおぺとやるとすごく面白くなるんですよね。私も「一緒にやりたい」と思っていましたし、俳優としてのおぺのことも「うらやましいな」と思っていました。
当時からみんなに一目置かれていたんですね。そんな中島さんから一緒に「いいへんじ」をやろうと声をかけられたときは、どうでしたか?
松浦:もう、超うれしかったですね(笑)。劇団に入れたらいいなとか、誰かと一緒にやっていこうというのは思っていなかったので、自分が「やった!うれしい!一緒にやる!」と返事をしたことにも結構驚きました。予想していなかったけど、そのまま乗っかっちゃえるくらいにはうれしかったです。
二つ返事でOKだったんですね。
松浦:即答でしたね。
いいへんじのこれまでの活動について、印象的なエピソードはありますか?
松浦:私とおぺは、割と喧嘩をするんです。お互い、雰囲気よく演劇を作ろうと努めているんですけど、自分自身のことになると、色々なものを投げ捨てて演劇をやってしまうんです。お互い苦しいところに自分を追い込んで演劇をやってしまうという面があるので、「良くない雰囲気」になることもあります。だから「いいへんじ」は楽しいというだけではなく、すごく切実で一生懸命というか…。私にとってそうなれるのが今のところ「いいへんじ」しかないんです。健康に良いかと言われると、良くも悪くもだと思うんですけど、私はそういったことをすごく必要としているので、続けてしまっています。
お互い本音でぶつかりあえるというのは、すごく素敵なことだと思います。
松浦:全然今も、なんでも言い合えるような気持ちのいい関係性ではないと思うんですけどね…(笑)。2017年に「いいへんじ」の旗揚げ公演『ハイ』を上演したときに、「うお、ちゃんと苦しい!」と思って。そこから、波はあるんですけど、ずっと苦しい感じがしています。
苦しさを共に味わえる関係性、でしょうか。
松浦:そうですね。すごく貴重な存在だなと思います。……こんなこと思ってるの私だけだったらすごく恥ずかしいですね…!
こういったことは普段、カンパニーの皆さんで話されたりしますか?
松浦:たまに、要所要所で話します(笑)。最近は定期的にミーティングだったり、公演が終わったあとの反省会をするようにしているので。公演中に思っていたことは話せる場をつくるようにしています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場より
作品についてお伺いします。これまでの「いいへんじ」の作品は松浦さんの目にどう映っているのでしょうか?
松浦:おぺの書く戯曲で一番良いのは「言葉」で、ほぼ「しゃべり言葉」で作られているんです。それを読むだけで、もう「いいへんじ」だとわかります。そういう作品をずっと作り続けていて、かつ、おぺは「言葉」というものをいつもブラッシュアップしようとしています。だから、とにかく戯曲の「言葉」が好きだなと思うし、それはずっと変わらないです。今回も、「言葉」がいとおしいです。全部。話す単語、喋り方、順序とか、選ぶ言葉がすべていとおしいなと思います。
おぺは「俳優本人の魅力を引き出して、いとおしい人間を描きたい」と言っていて、私は出ている人間として、「かわいい」とか「いとおしい」と言われることに違和感や疑問があって。それはたぶん、私自身が「人間ってそんなにいとおしいものではなくない?」と思ってしまっている部分があるからなのかもしれません(笑)。あと、「かわいいって簡単だよな」とか。だから、このままだと私自身がちょっとまずいんじゃないかと思っていたんですね。いとおしさみたいなものが「いいへんじ」の良い部分だということもわかってはいたんですけど。
でも今回の『薬をもらいにいく薬(序章)』は、通しを見て、そういった今までとは少し違う、嫌じゃない「いとおしさ」があったんです。なんでなのかは、まだわからないんですけど…。もしかしたら、俳優がみんな誰も自分を「いとおしくみせよう」と意図していないからかもしれないですね。「これをやろう!」ということ、目の前のやるべきことに集中しているから、そういった切実さがちゃんと「いとおしく」見えるということが起こったのかもしれないです。自分のことを「いとおしい」、「かわいい」と思っている人が登場するわけではないので、当たり前なのかもしれないんですけど…。見ていて、心がぎゅーっとなりました。
現実を生きる人のひたむきさ、みたいなものが感じられる作品に仕上がってきているんですね。拝見するのが本当に楽しみです。では、普段松浦さんが俳優として、作品に向き合う際に意識されていることや目標を教えてください。
松浦:「いいへんじ」の現場だと、「誰よりもおぺの書く言葉をすばらしく魅力的に扱える人になる」といつも思っています。そういう人になりたいなと。今までの作品を全部合わせて、おぺの書く台詞を1番多く喋っているのは私になると思うんですが、「おぺの言葉をすばらしく扱う」ことでは、誰にも負けたくないです。
他の現場だと、多分意識していることは毎回違うんですけど…。「おばあちゃんになるまで俳優をやろう」とは思っています。あと、今年、私は青年団という劇団にも新しく所属しまして、個人的に今すごく地方公演に興味があります。東京以外の土地で、泊まり込みで、演劇をたくさんやりたいです。
良いですね、前回の「コトリ会議」さんのインタビューでも、山本正典さんが旅公演の魅力を語ってくれました。
松浦:はい、すごく良いなぁと思って読みました(笑)。「いいへんじ」としては「将来こうしていこう」というしっかりとした目標を作ることはあまりないです。私たち自身、この先どういう風に演劇をやるかわからないし、他に素敵なやりたいことができるかもしれないと思っているので。でも、どんなときでも、「いいへんじ」に戻ってきたら息ができるように、というか、何かを持ち帰れる場所にしたいなと思っています。
松浦さんご自身が演劇をやっているのは、そういった「息ができる場所」という思いがあるからなのでしょうか。
松浦:演劇が他の表現と比べて特別だということはないと思っています。たまたま私にとっては、演劇が「息ができる場所」だったというだけなんです。演劇をずっと続けているのはきっと得意だからです。大きな声を出したり、台詞を覚えたりすることが得意。得意なことや、普段生きていてつい気になってしまうことを、演劇をつくる場では無視したり隠したりしなくていい。私にとってはたまたまそれが演劇だったというだけなんです。
最後に、芸劇eyesの上演に向けた作品づくりへの意気込みをお聞かせください。
松浦:うーん意気込み…。芸劇は憧れの場所です。「弱いい派」って言われているけど、きっと弱いだけだったら芸劇ではやれていないだろうと思います。強い気持ちを持って挑戦したいです。今回、私は声の出演というかたちにはなりますが、すごくワクワクしています。
松浦さんの声が芸劇にどのように響くのか、とても楽しみです。ありがとうございました!
松浦:ありがとうございました!
「いいへんじ」の松浦さんにお話を伺いました。5歳のころに地元・福岡の市民劇団に入り、演劇を始めたという松浦さん。「ずっと続けてるといいことありますね」と話してくださいました。
次回は、「ウンゲツィーファ」さんの稽古場に潜入します。
作品タイトルが『Uber Boyz』に決まった「ウンゲツィーファ」さんが、どのように稽古をされているのか、謎に迫ります。
お楽しみに!
稽古場インタビュー
いいへんじ 作・演出:中島梓織さん

トップバッターは、「いいへんじ」作・演出の中島梓織さんです。
『薬をもらいにいく薬(序章)』の稽古場にお邪魔し、フレッシュな素顔に迫りました。
中島さん、本日はよろしくお願いいたします。つたない進行で恐縮ですが、色々とお話お聞かせください…!
中島梓織さん(以下、中島):よろしくお願いします!今回はじめて私たちを知ってくださる方もいると思うので、良いきっかけになればと思っています。
ありがとうございます!まず、お伺いしたいのが、「いいへんじ」という団体名についてなのですが…由来があったりするのでしょうか?
中島:由来というものは実は特に無くて(笑)大学1年生のときに、私と松浦みる(俳優、「いいへんじ」所属)が早稲田大学演劇倶楽部というサークルで知り合ったんですけど、新人公演が終わって、自由に活動できるようになったときに、私はもともと劇作と演出がやりたいと思っていたので、「ユニットを作ろう」と。松浦に私から「一緒にやろう」と声をかけました。一緒にやっていくには名前が必要だよね、となったとき「ひらがなで、略せずに読める名前」にしようということで、候補を出し合って決めました。特にこだわりがあったわけではないんですが、「ちゃんとフルネームで呼んでほしい」という気持ちはあったかもしれないです(笑)お互い50個ずつ、思いつく単語を出し合いました。
50個も!
中島:はい(笑)そこから候補を絞って、最終的にお互いが「良いね」となったのが「いいへんじ」でした。だから意味とかは、あまり考えてなかったです。ただ、後付けですけど、「演劇をやる上で互いに応答しあうことが大事」ということはもともと考えていて、そこにたまたまはまったので「答えを出すことよりも、わたしとあなたの間にある応えを大切に」というのをキャッチコピーみたいに使うようになりました。
中島さんのこれまでの活動についてお伺いします。演劇は大学から始められたのでしょうか?
中島:本格的にはそうですね。大学1年生のときに「いいへんじ」を結成して、大学2年生のときに旗揚げ公演を早稲田大学の学生会館で打ちました。基本的には学生会館にある公演ができるスペースと早稲田小劇場どらま館を拠点に公演を行いつつ、外部の演劇祭やショーケースにも参加していました。特に大学2~3年生のときはハイペースに公演を行っていました。
大学以前は演劇と関わりはありましたか?
中島:高校生の時に演劇部に所属していました。そのときの顧問の先生から「演劇やるなら早稲田だよ」と勧められて、早稲田大学を受けて…という感じです。早稲田大学を志願しようと決めてからは、一直線でしたね。
もし演劇をしていなかったらこんなことをしていたかも、という職業はありますか?
中島:なにしてただろう(笑)難しいんですけど、学校の先生になっていたかもしれないです。中学生頃までは、周りの期待に応えようとしていたというか、典型的な「優等生」を演じていたので。中学校では生徒会長もやっていましたね(笑)
すごい!
中島:そういうイメージが外側からも出来上がっていたし、自分の中でも作っていた、というのが小学校・中学校のときはあったんですけど、そこから外れさせてくれたのが演劇でした。小・中とバスケをやっていて、体育会系のノリも自分には合っていなかったはずなのに無理をしてやっていて、もっと自分を自由に表現したいと思っていたところで演劇部に出会いました。「私のやりたいことはこれかもしれない!」と思って。そこから、約15年積み重なっていたものから徐々に解き放たれて…という。まだ完全に解き放たれきってはいないですが(笑)なので、演劇をしていなかったら学校の先生になっていたと思います。両親が教員ということもありますし、人に話したり、教えたりすることは好きなので。
作品についてお聞かせください。稽古進捗はいかがでしょうか?
中島:脚本の第1稿は上がっていて、俳優と話をしながら手直ししつつじっくり進めて行っている状況です。今日(取材日の6月20日(日))からバンバン立ち稽古を始めていこうかなと。
自分では脚本執筆は遅い方だと感じていて。なので今回は早めに、年明けくらいから手を付け始めていました。最初の構想から半年くらいかけていますね。プロットに時間をかけて、台詞を書き始めたのが4月中旬くらいからです。年を追うごとにいろいろと悩むようになってしまって、書くのが遅くなっている気がします…(笑)なので、自分で締切を決めて、周りに「この日までに上げます!」と宣言して自分を追い込みました。
めちゃめちゃストイックですね…!今回の作品の内容について、お話しいただける範囲でお聞かせください。
中島:5人の登場人物がいて、その中の2人の男女を中心に進んでいきます。2人の会話の中から、社会的にいわゆる“弱者”として括られてしまうような人たちを描こうと思っています。具体的には、精神疾患を持っている方々や、セクシュアルマイノリティの方々のような社会的に“弱者”と“されてしまっている”人たちです。彼ら彼女らにも生活や望みはあって、それを「どうにかしたい」と思っているのに「どうにかできない」ままに“させられてしまっている”という現状について、凄く時間はかかるけれど、対話の中で考えていければと思っています。なので、40分の短編の中では収まりきらず、今回は長編の冒頭を上演するという形になりました。時間をかけて、おしゃべりしながら、わたしたちなりの社会に対する応答を見つけていくことができればと思っています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場にて撮影
とはいえシリアスにはなりすぎず、俳優の力も借りて、コミカルさだったり、ポップさみたいなのも出せればと思っています。ずーんと重くなりすぎないのだけれど、劇場を出るときにちょっと考えてもらえるきっかけになればいいなと。
「いいへんじ」さんは、作品の内容とそれに対する向き合い方のバランスが絶妙だなと感じるのですが、そのあたりはどう意識されていますか?
中島:最近気付いたんですけど、劇作より演出の方が好きだなというのがあって。劇作が年々キライになっているというか……。
えー!
中島:キライというか、辛くなってきている、というか……(笑)やっぱり劇作は1人の孤独な作業というか、自分の中で考えを巡らせていかなければならない、自分が普段見ないようにしているところも見るようにしなければならないので、すごく辛くなりながら書いているんです。けど、演出はすごく楽しくて。いつも稽古前に皆でおしゃべりをする時間をつくるようにしているんですね。作品に関係するようなことを稽古前に話してから、作品の稽古に入るんです。自分が書くものは、ひとりで必死になって、何かを吐き出すように書いているものなんですけど、他の人にとってはぜんぜん違う見え方になるんだなって。稽古はその発見ができる場所だと思っています。そういういくつもの発見を1つの演劇に立ち上げていくという作業がめちゃくちゃ楽しいなと、最近どんどん自覚しています。なので、演出したいから書いている、みたいなところがあるかもしれません。これをきっかけにみんなとおしゃべりをするための準備だから頑張ろう、みたいな感じで書いていて。演出をするときは、俳優のみんなを魅力的にみせたいなという気持ちがあって、何かキャラクターを演じてほしいというよりは、その人自身の魅力を引き出せたらいいなということに注力しています。テーマ自体も、「重いな、暗いな」とかではなく「興味深いな」と思ってもらえることが一番大事だと思っていますね。重そうで暗そうなものでも、演劇の形にしてみると意外とおもしろく思えてきませんか?という提示をするための演出を考えています。

『薬をもらいにいく薬(序章)』稽古場にて撮影
『つまり』という作品があって、自分の実体験をそのまま赤裸々に、日記を書くみたいに書いたものなんですけど、それが出来たときは本当に恥ずかしくて。これは人様に見せられるようなものではない、という気持ちがありました。でも、逆にこれを人様に見せられる形、面白いと思ってもらえる形にするにはどうすればいいんだろう、という風に考えるようになりました。劇作家の自分に対して「なんてものを書いてくれたんだ!」という距離感で演出家の自分が演出する、みたいなことをまずは意識的にやるようにしていますね。
ご自身の生み出したものへのこだわりに対する冷静さがありますよね。影響を受けた作品などはありますか?
中島:上京してきて初めて観た演劇が、「贅沢貧乏」さんの『ハワイユ―』という作品でした。松浦も観ていましたね。山田さん(「贅沢貧乏」主宰:山田由梨)の軽やかさというか、お洒落さ、ポップさがすごく好きだなと思って。演劇や自分の書いたもの、俳優さんの魅力を「面白がる」のが上手な方なので、尊敬しています。
最初は書いている自分と演出をしている自分がごっちゃになっていたんですけど、最近は分けなきゃなと思っていて。劇作家が稽古場にいると答えがそこにあるような気がしてしまうので、「劇作家の中島梓織さんはここにはいません」みたいなことを俳優に言っていたりします。私はこの作品をみんなと一緒に読む側の人です、というスタンスでいるようにしています。俳優のみなさんがどう思っているかはわからないですけど…。自分のこだわりを皆にやってもらうというよりは、「こだわりもって書いたらしいよ!」とケラケラ笑いながら渡すような感じですね。
クリエーションの中でも「応答」を意識されているんですね。最後になりますが、芸劇eyesへの意気込みを教えてください。
中島:めっちゃ緊張してます。いつもの3~4倍くらい(笑)
それはショーケース形式という部分でですか…?
中島:いや、どちらかというと我々ショーケース芸人のようなところがあるので(笑)ありがたいことに演劇祭やフェスに呼んでもらうことが多くて…。なので、そこに対してというよりは、大きい劇場でやることに緊張しています。普段は小さい劇場で、お客さんが近いところでやっているので、結構個人的なことだったり、話題として小さいことを扱っていてもあまり違和感がないというか。それをどうやって芸劇の広さで成立させるか、効果的に魅せるにはどうすればいいか、試行錯誤中です。
なるほど、芸劇という空間へどう「応答」されるのか、楽しみです。中島さん、本日はありがとうございました!
中島:ありがとうございました!
「いいへんじ」の中島さんにお話を伺いました。
稽古場ではコミュニケーションゲームや話し合いの時間がしっかりと取られているのが印象的で、「コミュニケーションの中で見つかるもの」を大事にされていることを実感しました。
等身大の口語や、言語化しづらい感覚を丁寧に台詞に起こした会話は必見です。
次回ご紹介するのは、ウンゲツィーファの本橋龍さんです。
6月17日(木)~20日(日)に行われていたUL公演『トルアキ』を観劇し、終演後、お話を伺いました。
お楽しみに!